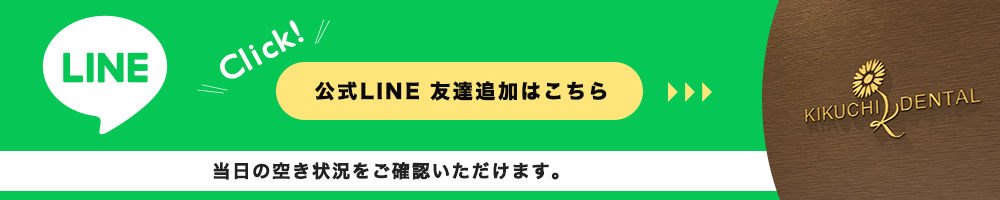歯磨きしても歯がざらざらするのはなぜ?原因と対策を解説 blog
2025.08.20

毎日きちんと歯磨きをしているはずなのに、「歯の表面がなんだかざらざらする…」と感じたことはありませんか?
歯のざらつきは、単なる磨き残しだけでなく、口腔内のトラブルのサインである場合もあります。
本記事では、「歯磨きしてもざらざらする原因」「正しい歯磨きの仕方」「予防歯科の大切さ」についてわかりやすく解説します。
歯磨きしてもざらざらする5つの主な原因
1. 歯垢(プラーク)の磨き残し
歯磨きの時間や回数は足りていても、歯の表面や歯と歯の間、歯ぐきとの境目に歯垢(プラーク)が残っていることがあります。歯垢はねばねばした細菌のかたまりで、歯の表面に残るとざらつきを感じることがあります。
とくに奥歯や歯の裏側などは、丁寧に磨かないと汚れが残りやすく、ざらざらの原因になります。
2. 歯石の蓄積
歯垢が唾液中のミネラルと結びついて硬くなると「歯石」になります。歯石になると、通常の歯磨きでは落とすことができません。歯石は表面がザラザラしており、その上にさらに汚れが付きやすくなる悪循環を招きます。
特に下の前歯の裏側や、上の奥歯の外側にできやすい傾向があります。
3. ステイン(着色汚れ)
コーヒーや紅茶、赤ワイン、カレーなど色の濃い飲食物を頻繁に摂取していると、歯の表面にステイン(着色汚れ)が付着します。喫煙もその大きな原因です。これも歯の表面のざらつきとして感じられることがあります。
4. エナメル質の摩耗やダメージ
強い力で歯を磨いていたり、研磨力の強い歯磨き粉を使用していたりすると、歯の表面を覆うエナメル質が削れ、ざらざらとした手触りになることがあります。エナメル質が摩耗すると、見た目のくすみや知覚過敏の原因にもなります。
5. 虫歯や歯周病の初期症状
初期の虫歯では、歯の表面がわずかにざらついたり、白く濁って見えることがあります。また、歯周病により歯ぐきが下がると、露出した歯の根元がざらざらに感じられることも。
ざらつきが続く場合は、放置せず歯科医院でのチェックが必要です。
ざらざら感を防ぐ正しい歯の磨き方
1. 力を入れすぎない磨き方
「強く磨いた方が汚れが落ちる」と思っていませんか?実はこれは間違いで、強すぎるブラッシングは歯や歯ぐきを傷める原因になります。
歯ブラシは鉛筆を持つように軽く持ち、100〜150g程度の軽い力(歯ブラシの毛先が少ししなる程度)で磨きましょう。
2. 歯ブラシの角度と動かし方
歯と歯ぐきの境目に45度の角度で歯ブラシを当て、小刻みに動かします。1本1本を丁寧に磨く意識が大切です。奥歯や歯の裏側、歯並びの悪い部分は特に磨き残しやすいため、意識して磨くようにしましょう。
3. デンタルフロスや歯間ブラシの活用
歯ブラシだけでは、歯と歯の間(歯間部)の汚れは落としきれません。毎日のケアにデンタルフロスや歯間ブラシを取り入れることで、ざらざらの原因となる歯垢や食べかすを効果的に除去できます。
4. 歯磨き粉の選び方
研磨力が強すぎる歯磨き粉は、エナメル質を傷つける可能性があります。ざらざら感が気になる方には、低研磨性でフッ素入りの歯磨き粉がおすすめです。ステイン対策にはポリリン酸やピロリン酸ナトリウム配合の製品も効果的です。
ざらざらを予防するには?予防歯科のすすめ
日々のセルフケアはもちろん大切ですが、自分では落とせない汚れや歯石を除去するためには、定期的な歯科医院でのチェックとケアが欠かせません。
1. 歯科での定期クリーニング(PMTC)
専門の器具を使って歯科衛生士が行うPMTC(プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニング)では、普段の歯磨きでは取りきれない汚れや着色を除去できます。歯の表面をなめらかにし、再び汚れが付きにくい状態に整えます。
2. ライフスタイルの見直し
- コーヒーや紅茶、タバコなどの着色物の摂取量を控える
- 食後のうがいや水分補給を習慣にする
など、ちょっとした工夫で歯のざらつきやステインを防ぐことができます。
3. フッ素塗布やシーラント
虫歯予防の一環として行うフッ素塗布やシーラント処置は、歯の表面を保護し、ざらざらの原因となる虫歯や歯垢の付着を防ぐ効果があります。
まとめ|ざらざらする歯は早めに歯科医院でチェックを
歯のざらつきは、単なる汚れかもしれませんし、初期の虫歯や歯周病のサインであることもあります。どんなに丁寧に磨いていても、セルフケアだけでは落としきれない汚れは存在します。
ざらざら感がなかなか取れない方、定期的なケアができていない方は、ぜひ一度ご相談ください。
当院では、患者さま一人ひとりのお口の状態に合わせたケアや予防歯科をご提案しております。