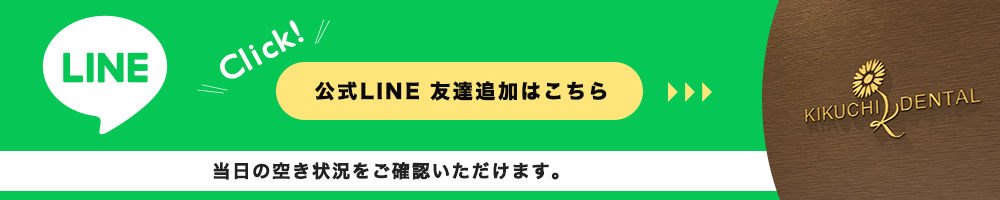歯並びが悪いとどうなる?原因・影響・改善方法をわかりやすく解説 blog
2025.10.20

「歯並びが悪い」と感じている方は少なくありません。鏡を見たときに前歯が重なっていたり、かみ合わせがずれていたりすると、見た目の印象だけでなく、日常生活においてもさまざまな影響が出ることがあります。
この記事では、「歯並びが悪い」というテーマをもとに、その原因、体への影響、セルフケアのポイント、改善の選択肢についてわかりやすく解説します。
「歯並びが悪い」とはどういう状態?
一般的に「歯並びが悪い」とは、歯がまっすぐに並ばずに重なったり、隙間が空いていたり、上下のかみ合わせがずれている状態を指します。医学的には「不正咬合」と呼ばれ、以下のような種類があります。
叢生(そうせい):歯がデコボコに並んでいる状態。顎の大きさに対して歯が並ぶスペースが足りないと起こります。
出っ歯(上顎前突):上の前歯が前方に突出している状態。指しゃぶりや舌の癖なども原因の一つといわれます。
受け口(反対咬合):下の歯が上の歯よりも前に出ている状態。成長期の顎の発育が影響する場合があります。
開咬:上下の歯をかみ合わせても前歯が開いてしまう状態。口呼吸や舌の位置の問題が関係することがあります。
すきっ歯(空隙歯列):歯と歯の間に隙間がある状態。歯の大きさや本数、顎の大きさのバランスが影響します。
このように「歯並びが悪い」といっても、その状態はさまざまです。
歯並びが悪い原因とは?
歯並びが悪くなる原因は一つではなく、複数の要因が重なって起こります。主な要因を見ていきましょう。
遺伝的な要因
顎の大きさや歯の大きさは遺伝的な影響を受けやすいため、家族に歯並びの悩みを持つ人がいると似た傾向が出ることがあります。とくに受け口は遺伝的要因が強いです。
生活習慣や癖
幼少期の指しゃぶり、舌を前に押し出す癖、頬杖、口呼吸などは歯や顎の成長に影響を与えることがあります。
永久歯への生え変わり
乳歯の抜けるタイミングや、永久歯の萌出(はえ方)によって歯列が乱れることもあります。
顎の発育
顎の骨の成長が不十分、あるいは過剰な場合も歯並びやかみ合わせに影響します。
歯並びが悪いと起こりやすい影響
「見た目だけの問題」と考えがちですが、歯並びが悪いことは口の中や体全体にも影響を与えることがあります。
清掃不良によるリスク
歯が重なっていると歯ブラシが届きにくく、プラーク(歯垢)が残りやすくなります。その結果、むし歯や歯周病のリスクが高まることがあります。
かみ合わせのバランス
歯並びが悪いと、一部の歯に強い力がかかり、歯が欠けやすくなったり顎関節に負担がかかることがあります。
発音や咀嚼への影響
すきっ歯や開咬などでは、発音がしづらかったり、食べ物をよく噛めないことがあります。
見た目の印象
歯並びは笑顔の印象に大きく関わります。整った歯並びは清潔感や自信につながることが多い一方、歯並びが悪いと口元を隠したくなる人も少なくありません。
歯並びが悪いと感じたときのセルフケア
歯並び自体をセルフケアで治すことは難しいですが、悪影響を最小限に抑える工夫は可能です。
毎日の歯磨を工夫する
歯間ブラシやデンタルフロスを活用し、歯の重なり部分や隙間もきちんと清掃することが大切です。
定期的な歯科検診
歯並びが悪いとむし歯や歯周病のリスクが高くなるため、歯科医院で定期的にクリーニングやチェックを受けましょう。
生活習慣の見直し
口呼吸や頬杖などの癖を改善することは、これ以上の歯列の悪化を防ぐ一助となります。
歯並びを改善する方法
「歯並びが悪い」と感じるとき、改善を考える方も多いでしょう。ここでは一般的な改善方法を紹介します。
矯正治療
歯並び改善の代表的な方法です。ワイヤー矯正、マウスピース矯正などさまざまな装置があります。治療法は年齢や歯並びの状態によって異なり、期間や費用も幅広いため、気になったら早めに歯科医院で相談することが大切です。
補綴による方法
軽度のすきっ歯や歯の形の問題の場合、セラミックやジルコニアの被せ物などで見た目を整えることもあります。
口腔習癖の改善
子どもの場合は、舌の位置や指しゃぶりなどの癖を改善するトレーニング(MFT:口腔筋機能療法)が効果的なこともあります。
歯並びを放置するとどうなる?
「多少歯並びが悪いくらいなら大丈夫」と思って放置すると、長期的に以下のような問題が出る可能性があります。
- むし歯や歯周病のリスク増加
- 顎関節症のリスク
- 歯のすり減りや欠けやすさ
- 見た目のコンプレックスによる心理的影響
早めに歯科で相談し、自分に合ったケア方法や改善策を知ることが大切です。
まとめ
「歯並びが悪い」といっても、その原因や状態は人によって異なります。
歯並びは見た目だけでなく、健康や生活の質にも関わる大切な要素です。
- 歯並びが悪い原因には、遺伝・生活習慣・顎の成長などがある
- 歯並びが悪いとむし歯や歯周病のリスク、かみ合わせや発音への影響がある
- セルフケアでリスクを減らしつつ、必要に応じて歯科で相談することが大切
自分の歯並びが気になるときは、まずは信頼できる歯科医院で相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。